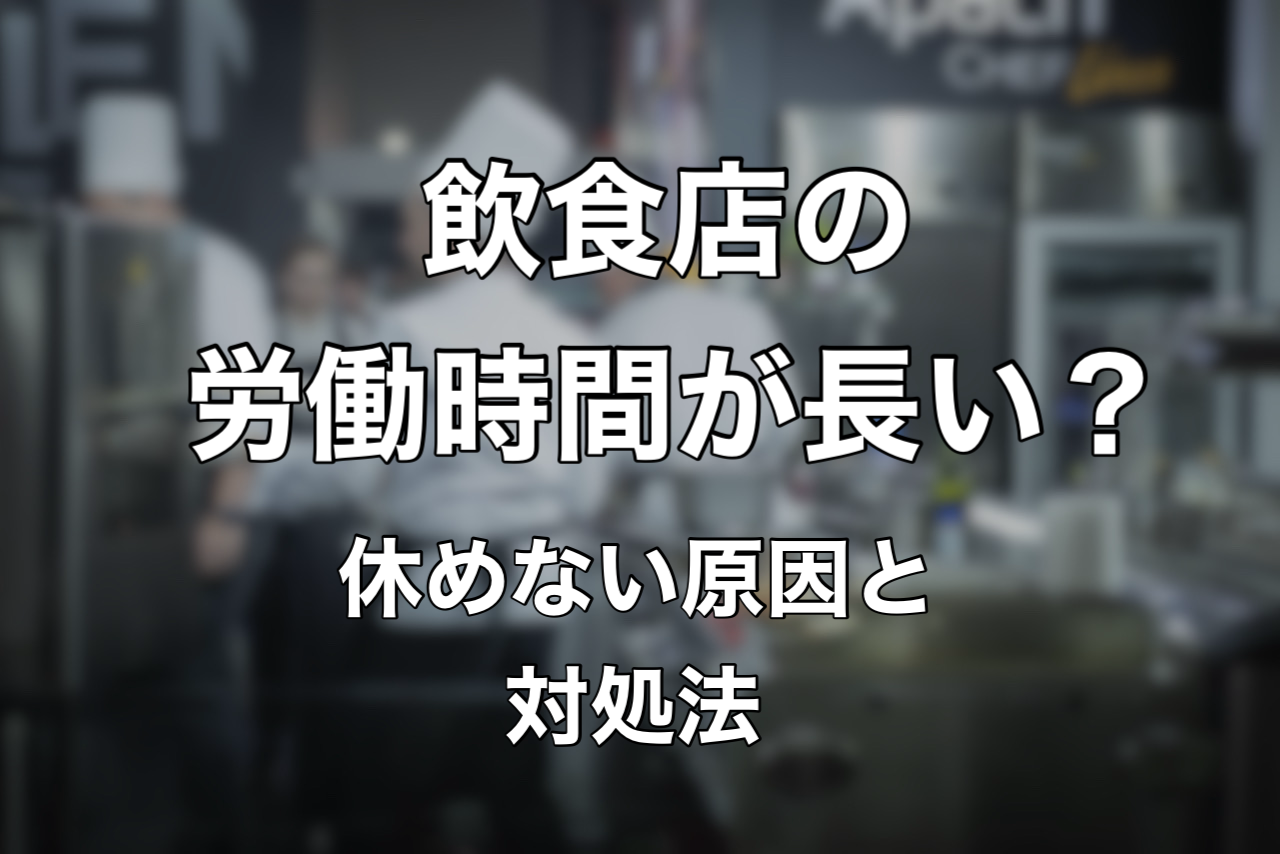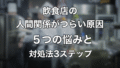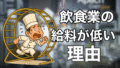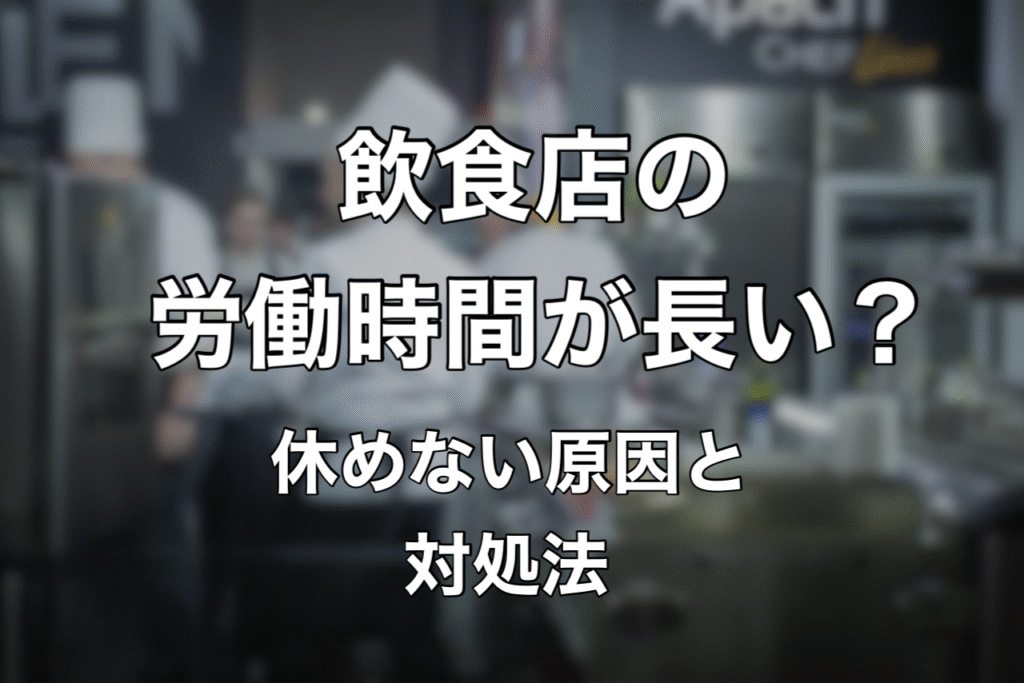

飲食店で働いていると一日が過ぎるの、あっという間だよね。
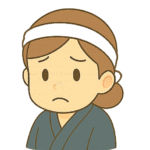
そうそう、休まる時間がないって感じだよ。
私も新人時代は、誰より早く店に行き漂白してあった、まな板やダスターを洗って備品を配置。
先輩周りのセッティング、仕込み、開店準備からの営業。
休憩もまともに取れずに、夜営業の準備。
閉店後は片付け、翌日の発注などで毎日ヘトヘト・・・。
早く帰って休みたいけど、みんなが残っていて帰れない雰囲気。
気づけば毎日終電ギリギリ、家に着くころには日付が変わっている、そんな日々でした。
ここでは、自身の体験も交えて飲食店の労働時間の長さの原因と対処法について解説します。
「もう限界かも…」と感じているあなたのヒントになれば嬉しいです。
・飲食店で労働時間が長くなりやすい理由
・長時間労働が心身やキャリアに与える影響
・今日からできる改善策と、環境を変える選択肢
なぜ飲食店は労働時間が長くなりやすいのか
飲食店の長時間労働は、ただ「忙しいから」だけではありません。
実際、繁盛していない店でも拘束時間は変わらず長く、逆に繁盛している店よりも労働環境が悪化しているケースもあります。
これは、いくつかの要因が重なって、結果的に拘束時間が長くなる構造になっているからです。
飲食業の労働時間と法律の基準(労基法)

日本の労働基準法では、1日8時間・週40時間が原則だよ。
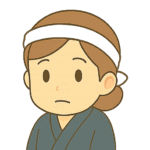
残業(時間外労働)は 月45時間・年360時間だからね。
しかし飲食店では、この基準を大きく超える勤務時間になることも珍しくありません。
「36協定(さぶろくきょうてい)」という労使協定を結べば残業は認められますが、
特別条項付き協定でも年間720時間まで、1ヶ月100時間未満といった制限があります。
それでも実際は、残業代がつかない「サービス残業」や、シフト外の仕込み作業が横行している店も少なくないのが現実です。
労働基準法は「守るべきルール」ですが、現場ではグレーなケースがほとんどです。
まずは自分の労働時間を把握して、基準とどれくらい差があるかを知ることが第一歩です。
実際の現場では、これを大きく超える勤務をしている人も多く、「みんなやってるから仕方ない」となりがちです。
営業前後の業務で拘束時間が長くなる
飲食店の労働時間が長くなる大きな理由のひとつが、営業前後の業務です。
実際には「営業開始~終了」の時間だけが仕事ではありません。
営業前:開店の数時間前に出勤して、掃除・セッティング・仕込み。
営業後:閉店後の片付け・洗い物・翌日の仕込み・ミーティングなど。

実際のところ、営業時間外の方が業務があったり、神経使ったりするんだよね。
これらを含めると、拘束時間は12時間を超えることは日常です。
営業時間が過ぎても、すぐに帰らないお客さんも当然います。
片付け作業も遅れるし、そのあとにスタッフ間でのミーティングもあったりします。
やっと家に着いたら、寝るだけで朝が来る、そんな日々が続きます。
問題なのは、これらの時間がタイムカードに含まれていないケースが多いことです。
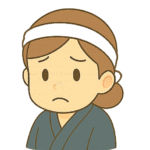
以前働いていた会社では、ミーティングは時間外扱い。
休日にも参加させられてたよ。
表向きの労働時間は8時間でも、実際は10~12時間、それ以上拘束されている人も多いでしょう。
営業前後の業務は必要な仕事ですが、仕込みや片付けの効率化、発注の仕組みを整えるだけで大きく短縮できることもあります。
現場にいると「こういうものだ」と思い込んでしまいますが、改善できる余地は意外とあります。
人員不足と業界特有の「やりがい搾取文化」
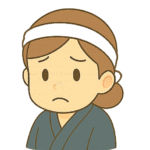
人手不足がそもそもの問題なんだよ。
飲食業界では慢性的な人手不足が当たり前になっています。
その結果、少ない人数で店を回すのが常態化し、「長時間働くのが当たり前」 という空気が根付いてしまっています。
私が働いていた店でも、スタッフが辞めてもすぐに補充されず、残ったメンバーでシフトを埋めるしかありませんでした。

常に人が足りていない店は、そもそも環境が悪いから
新人が入ってもすぐに辞めていくんだよ。
気づけば一人あたりの負担が倍増し、休みも減っていく悪循環…。
さらに厄介なのは、上の立場の人が
「俺たちも昔はもっと働いてた」
「これくらい耐えられないと一人前じゃない」
「間に合わないのは仕事が遅いからだ」
とプレッシャーをかけてくること。
こうした雰囲気は、いわゆる
「やりがい搾取」 と呼ばれる文化です。
「好きでやってるんだから頑張れるよね」と無意識に思わせることで、長時間労働を正当化させやすくなります。
実際、アルバイトスタッフの方が時間でしっかり管理されている分、早く帰れるし働きやすいと感じることもありました。
正社員や役職者ほど「帰りづらい」「残るのが当たり前」という空気に縛られてしまいます。
休憩がとりづらい空気と職場の雰囲気
労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない、と定めています。出典:厚生労働省HP

実際、ゆっくり休んでる状況じゃない事の方が多いんだよ。
飲食店は休憩時間も「決まって取れる」とは限りません。
法律では、6時間を超える勤務なら45分以上、8時間を超える勤務なら1時間以上の休憩が必要です。
現場ではお客様の入り具合や忙しさ次第で休憩がずれ込んだり、取れないまま終わることもあります。
私も新人時代、「今休んでいいよ」と言われても、
周りがまだバタバタ動いているのを見ると休みにくくて、結局まかないをかき込んで終わり…なんて日がほとんどでした。
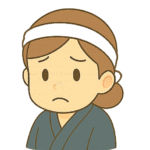
休んだら休んだで、なんか気まずい空気になったりするんだよね。
「お客様優先」が基本の業界だからこそ、どうしても休憩より現場の仕事を優先してしまいがち。
休憩を取ることが悪いことのように感じてしまい、体も気持ちも休まらないまま働き続ける事になったりします。
こうした「休みにくい空気」は、自分一人ではなかなか変えられません。
だからこそ、店長や責任者に相談して「交代で休憩を取る仕組み」を作ったり、せめて15分でも座って休めるタイミングを確保する工夫が大切です。
長時間労働がもたらすリスク
心身の疲労が回復しない

寝て起きても全く疲れが取れずに、時間に追われる毎日だった時期もあったな。
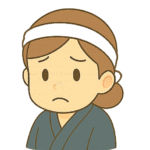
身体や心に異常が出る前に対処しないと大変なことになるよ!
長時間労働が続くと、当然ながら体と心に影響がでます。
・休んでも疲れが取れない
・短気になり、コミュニケーションがとれない。
・仕事のことを考えると気が重い
こんな状態が続いていませんか?
私も一時期、営業が終わると手足が震えるほど疲れて、家に帰っても座ったまま寝落ちしてしまう日々がありました。
次の日も朝から仕込みがあるので、しっかり休む間もなく、疲れが積み重なっていく感覚…。
心身の疲れが回復しないまま働き続けると、集中力や判断力が落ち、ミスも増えてしまいます。
「気合でなんとかなる」と思いがちですが、無理を重ねれば体を壊して、結果的に長期的な離脱を余儀なくされることもあります。
疲労が抜けないと感じたら、まずは今の働き方を見直すサインです。
・睡眠時間が確保できているか?
・心身の不調が続いていないか?
・ネガティブな思考になっていないか?
一度振り返り、必要ならシフトや業務量を調整する行動が大切です。
プライベートや家族との時間が失われる
飲食店は夜や休日が稼ぎ時。どうしても世間の休みとズレた生活になりがちです。

家族の行事事や、友人との集まりがあっても基本、土日。
参加できないのが当たり前だよね。
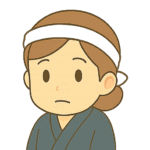
これはサービス業全般に言える問題だね。
土日や祝日はもちろん、クリスマスやお盆、年末年始も繁忙期で「家族や友達と過ごせない」という悩みをよく聞きます。
私も以前、年末年始の連勤で大晦日のカウントダウンは厨房、元旦は早朝から仕込みという年が何度もありました。
「今日は何曜日だったっけ?」とカレンダー感覚が麻痺してしまうこともありましたね。
家族行事や友人との約束を犠牲にし続けると、次第に孤独感や虚しさが積もっていきます。
特にお子さんがいる方は、学校行事や誕生日に参加できず、罪悪感を感じる人も多いでしょう。
こうした生活が続くと「仕事のために生きているのか…」とモチベーションが下がりやすくなります。
もし同じ悩みを抱えているなら
・平日休みを活かして、一人時間を充実させる
・家族と事前に休みを合わせて、特別な時間を作る
・思い切って働く時間帯を変える(ランチ営業の店に移るなど)
といった工夫で、バランスを取り戻すことができるかも知れません。
離職率の高さ・キャリア形成への影響
飲食業界は全体的に離職率が高い業種として知られています。
厚生労働省のデータによると、宿泊業・飲食サービス業の離職率は全産業の中でもトップクラス。
長時間労働や人間関係のストレスが続くと、心身が持たなくなり、せっかく育ったスタッフが次々と辞めてしまう現場も少なくありません。

理想と現実のギャップが激しくある仕事だからね。
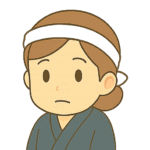
過酷な労働環境の割には給料も高くないし改善が難しいよね。
私自身も、入社してすぐに「同期の半分以上が辞めていた」という経験をしました。
残った人で回すためにさらに労働時間が伸びる → また誰かが辞める…という悪循環が起きやすいのが現実です。
長時間労働が常態化すると、自分のキャリアについてじっくり考える余裕がなくなり、
「ただ日々をこなすだけ」「気づけば数年経っていた」という状態になりがちです。
でも、時間は待ってくれません。
いつか独立したい人も、別の業態に挑戦したい人も、行動するなら体力も気力も残っているうちがおすすめです。
・「今の働き方が5年後・10年後も続けられるか」を考えてみる。
・長期的にキャリアを積める環境なのかを考えてみる。
・未来が想像できなのなら、早めに環境を変える。
この見直しだけでも、自分の未来がクリアになってモチベーションが回復することがあります。
長時間労働への対処法3ステップ
長時間労働は「気合い」や「根性」でどうにかなる問題ではありません。
ここからは、現場で今日からできる具体的なステップを3つ紹介します。
まずは自分の労働時間を「見える化」する

朝出勤して、終電で帰るが当たり前になってると
改善することすら考えないんだよね。
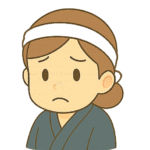
それ、客観的にみたら、かなり異常な環境だよ。
最初の一歩は、今の自分の労働時間を正確に把握することです。
「なんとなく長い」「しんどい」と感じていても、数字にしてみると客観的に状況が見えてきます。
・出勤・退勤時間をスマホでメモする
・営業前後の仕込み・片付けも含めて記録する
・1週間分まとめて、平均何時間働いているかを出す
私も初めて記録したとき、想像以上の時間を仕事に費やしていると驚きました。
数字で見えると「やっぱりこれは長すぎるな」と確信が持てるので、改善の行動に移しやすくなります。
現場でできる改善策を試す(休憩確保・シフト調整)
見える化したら、次は現場でできる工夫を試してみましょう。
・仕込みや片付け、仕事量の分担を見直す。
・休憩をきちんと取れるように責任者、同僚に相談する。
・シフトを調整して週に1日は完全休養日を確保する。

個人プレーになる人が多いから、任せる、手伝うを意識していくといいよ。
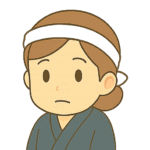
言い出しにくいかもしれないけど、一度は話して見る価値はあるよ。
現場はどうしても「みんな我慢してるから自分も…」となりがちですが、勇気を出して相談すると意外と受け入れてもらえることもあります。
改善されない場合は環境を変える(異動・転職)
努力しても変わらない場合は、職場環境そのものを変えることをすすめます。
私も以前、残業が当たり前の店から別の店舗に異動しただけで、労働時間が半分くらい短くなり、生活の質が一気に良くなった経験があります。

労働時間だけじゃなくて、仕事の内容も改善されて給料も上がる事もあるよ。
いままで、どれだけ搾取されてたんだ?と気づかされる。
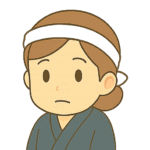
より良い環境で働けるように転職するのは、当たり前の事だからね。
異動が難しい場合は、転職サイトなどを活用して「労働時間が明確な求人」を探すのもおすすめです
最近は飲食業界でも「月8休」「残業代全額支給」を掲げる企業も増えてきています。
まとめ|無理しない働き方を選んでいい
飲食店はやりがいのある仕事ですが、長時間労働が続くと心も体も消耗してしまいます。
「みんなやってるから」「自分が頑張ればなんとかなる」と無理を重ねると、
気づかないうちに疲れが限界を超えてしまうこともあります。
まずは、自分の労働時間を見える化して現状を把握すること。
次に、できる範囲で仕組みやシフトを調整し、少しでも休める時間を増やす工夫をすること。
それでも改善が見られないなら、環境を変える勇気を持つこと。
働き方を変えることは、決して逃げではありません。
自分が抜けたら、迷惑が掛かるなんて考えることは一ミリもありません。
自分の事を大切にしてくれない職場を、こちらが心配する義理は無いです。
むしろ、これからも働き続けるために必要な行動です。

今日が人生で一番若い日だよ。
自分の未来のために動き出すなら、今がベストタイミング。
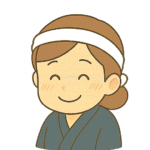
無理しないで。
ちゃんと休んで、元気に働ける場所を見つけよう
あなたの人生は一度きり。
やりがいを持って、安心して働ける場所は必ずあります。
少しずつ、自分に合った働き方を選んでいきましょう。